第7回『建築構造用高性能590MPa(N/mm²)鋼材(SA440)について』
北海道地区
KOBELCO WELDING VIRTUAL EXPERIENCE
溶接メタバース
学生フォーミュラ日本大会2024に出展
● 第17回
銅合金と和鏡・魔鏡
「鏡が割れると縁起が悪い」と言われてドキッとしたことがないだろうか。なぜか鏡には、さまざまな伝承・習俗から他愛のない迷信の類まで、とにかく逸話が付いて回る。
日本神道において、天照大御神(アマテラス)が地上にもたらした三種の神器のひとつ「八咫鏡(やたのかがみ)」は、伊勢神宮に奉安されていまも国を見守っているとされる。また、日本各地の神社の多くも、神の宿る依り代として御神鏡を本殿に納め、大切に祀って代々祈りを捧げてきた。信仰の有無に関わらず、日本で暮らしていれば地域の神社や神話はごく身近な存在で、畏敬の対象でもある。私たちが、つい鏡に神秘を感じてしまうのもあながち根拠のない話ではないだろう。
宝器・祭祀具から庶民の生活用品へ
金属鏡は、弥生時代前期に中国から伝来し、呪術・祭祀や魔除けの道具として用いられてきた。その後、平安時代以降には貴族や上流階級の人々が化粧や洗面に用いる実用品としても用途が広がった。鏡が一般庶民にとっても日常づかいの必需品になったのは、ずっと後の江戸時代後期であったとされる。当時は、急激に増えた需要に追い付くために、素材や品質の粗悪な鏡が数多く生産された時代でもあったようだ。
一方、現代の私たちに馴染みのあるガラス鏡は17~18世紀にヨーロッパから伝来したもので、明治20年代以降に日本国内でも広く普及した。取り扱いの容易なガラス鏡が安価に大量生産されるようになったことで、日用品としての金属鏡の需要は減少し、現在は主に神社仏閣の奉納鏡としてその姿を残している。
和鏡の製作
鋳造
和鏡は、複数の金属を溶かし合わせて成型する鋳造製品だ。使用する合金は主に青銅で、これは銅に錫と亜鉛を加えたものである。青銅よりも硬い、白銅(銅と錫の合金)を用いることもある。青銅は融点が低く、錫の含有量によって硬度を変えることができ、加工性に優れることから鋳造に適した素材とされる。
和鏡の背面には、さまざまな美しい文様が施される。これを成型するために用いるのが砂型である。固めた砂の上に「ヘラ」と呼ばれる道具で文様を刻んでいく。直径20cm程度の砂型を1枚完成させるのに、2~4か月もかかるという。
想定外の事態に備えて、通常は1枚の注文に対して最低2枚、場合によってはそれ以上の枚数の鏡を製作するが、鏡は砂型を割って取り出すことになるため、ひとつの砂型は一度きりしか使用できない。つまり、鏡の枚数と同じ数の砂型を作る必要があり、これだけでも数か月、ときに1年近くを要することもある。砂型が完成したら型を焼いて水分をとばし、溶かした金属を流し込んで固める。


削り・磨き
砂型から鏡を取り出したら、表面の凹凸を金属製のヤスリで削りとる。削る工程を経て、鏡は徐々に金属らしい光沢を増していく。ヤスリで削った後は、センという道具でさらに切削してヤスリ跡を整える。
削りの後は砥石で研ぎ、さらに水に濡らした木炭で鏡の表面を研ぐ。炭研ぎに使用する炭は、朴炭と駿河炭だ。これらは金属の研ぎだけでなく、漆など広く工芸品の研ぎに用いられる高品質の研磨炭で、鏡面に細かい傷を作らず繊細に研ぐことができる。最後の仕上げに鍍金(主にニッケル鍍金)を施すと、滑らかできめの細かい鏡面が完成する。


魔鏡の製作― 山本合金製作所
魔鏡とは、鏡に光を当てて反射光を投影すると、投影光の中に図案が現れる金属鏡のことだ。鏡面は、肉眼で見ただけでは普通の鏡との違いは全く分からない。実は、魔鏡製造の技術は過去に一度、途絶えてしまったものだ。現在ある製法は昭和49年、京都市にある山本合金製作所 3代目である山本真治(凰龍)さんが、資料もない中、文字通りの手探りで製法を解明して復活させたものだという。そこから現在に至るまで、山本合金製作所は、世界で唯一の魔鏡を製作できる工房である。
魔鏡現象は、金属鏡の鏡面を極限まで薄く削ることで起きる。薄く削った鏡面はフラットに見えるが、実際には目に見えない程のわずかな凹凸があり、光を当てると鏡背の文様が反射光のムラとなってあらわれる。鏡面を薄く削れば削るほど魔鏡は明瞭な像を投影するが、削りすぎれば鏡は破れてしまう。手に伝わってくる金属のわずかなたわみの感触だけを頼りに、1か月もの間、削り続ける。並外れた集中力を要する、繊細な仕事だ。
特に日本では、江戸時代の隠れ切支丹が弾圧を避けるために用いたとされる切支丹魔鏡が知られている。切支丹魔鏡の場合は、背面に刻まれた宗教的なモチーフの上から別の柄の板を被せて覆い隠す二重構造になっている。鶴亀や松竹梅など、ありふれた柄で生活用品を装って、その実は、苛烈な禁教下における人々の信仰の拠り所となったのだ。

経験が支える和鏡づくりの技術
山本合金製作所の創業は、江戸末期の慶応2年(1866)。当時、和鏡は庶民の暮らしの必需品だったが、金属製の鏡は長く使っているうちに曇ってしまう。そのため、鏡の定期的な磨き直しは鏡師の仕事のなかでも大きな割合を占めていた。
和鏡を新調するだけなら、何も手仕事でなくてもプレス機械を使って製造できるだろう。しかし、磨き直しは古い鏡の状態によって手入れを細かく調整する必要があり、手作業で鏡をつくる技術がなければ請け負うことはできない。
山本合金製作所では、長い間引き受けていなかった古い鏡の修復を5代目から再開している。ものを修理しながら長く使うことは、和鏡に限らず全ての工芸文化の本懐でもあると考えたからだ。また現代において、由緒ある和鏡の多くは神社の御神鏡として本殿奥に納められ、代々大切に祀られている。心情的にも、人々の祈りを受け止め続けてきた特別な品物を、無下にすることはとてもできない。
ただし、修復作業には特有の難しさがあるという。古い鏡を磨き直すと、それまでは曇りに紛れて気が付かなかった大小の傷がかえって目立って現れることがある。修復作業のせいで傷が増えたと勘違いされることのないよう、作業の前後には、必ず丁寧な記録と説明が必要となる。気がかりも多く手間のかかる仕事だが、結果として、寺社仏閣や博物館などさまざまな依頼者とのやり取りは、経験とノウハウを蓄積するための絶好の機会にもなった。
和鏡づくりは、細やかな手先の感覚が仕上がりの質を左右する。数世代前の職人による仕事を現代の職人が受け取り、磨き直して再び循環の輪の中に戻す。新調・修復を繰り返す日々の手仕事の積み重ねそのものが、職人の血肉となって、唯一無二の魔鏡製作を含む高度な技術の維持に繋がっているのである。


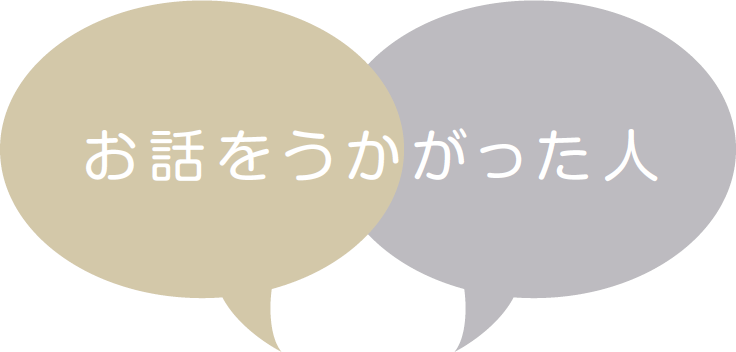
「山本合金製作所」
鏡師山本 晃久さん

山本合金製作所は、日本全国の和鏡の製作を一挙に担う「京都の鏡師」。5代目の山本晃久さんは、鏡師として初の無形文化財となった職人、真治(鳳龍)さんの孫にあたる。
「職人はいいものを作ることだけ考えていたらいい、いいものを作っていれば必ず次に繋がるんやからと。そう言いながら、祖父はいつも仕事を教えてくれていました」。
山本さんは、先々代の言葉をこう振り返る。ご自身は4代目である父とともに2014年に安倍元首相がバチカンを訪問してローマ法王に献上した切支丹魔鏡を、そして4代目は2016年、上皇陛下が橿原神宮に下賜された銅鏡「橿原の杜」の製作を手掛けたことで、それぞれ名を知られる鏡師だ。だが「どこのどなたの手に渡るものであろうと、職人は等しく最善の仕事をするだけ」と、山本さんも言う。
多くが信仰に関わる品物ということもあって、和鏡の新調・修復には他では替えの利かない切実な需要がある。しかし一方で、人々の信仰心が薄れゆき効率重視に傾く現代社会において、山本さんは、職人が技術の良さや希少性だけを訴えても、一般の人の共感を得ることは難しいことを痛感している。
だから山本さんは、多彩な現代アーティストとのコラボレーションの機会を大切にしている。彼らの表現は、職人と違って「コンセプトありき」。コンセプトに沿った空間演出や舞台装置として、和鏡がそこに置かれることに必然性と意味を与えてくれる。
「たとえばアート作品を通じて、和鏡のある空間の美しさとか、場の雰囲気全体に感動してもらえたら、そのほうがずっと広く、深く、より多くの人の共感を呼べると思うんです。和鏡で人に喜んでもらって、お互いが豊かになるような関係に向かう努力をしていきたい」。
どんな工芸品も、将来に伝えるためには人や社会から必要とされるものでなければならない。山本さんの鏡は、人々が過去から現在へと繋いできた祈りや願いを、きっと未来に連れていってくれるだろう。

 当サイトにつきましては、
当サイトにつきましては、